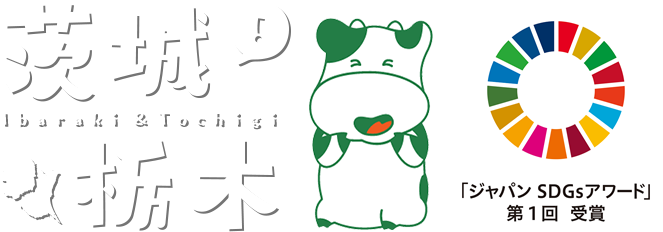テーマ別組合員活動
テーマ別組合員活動とは
地域に根ざしたテーマ別組合員活動「環境」「平和国際交流」「食育」「産直」の組合員活動をすすめます。
方針
環境
パルシステム「環境・エネルギー政策」並びにパルシステム茨城 栃木の環境方針に基づき、持続可能な「脱炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」に向けて取り組みをすすめていきます。
-
SDGsの基礎を学び、家庭でできるSDGsを広めます。
- 石けん利用を通じた水環境保全によるSDGs貢献
- 気候変動による影響とその対策等についての学びの場の提供
-
持続可能な社会をめざし、次世代を担う子どもたちに対して環境体験型企画を開催し、学んだことを実践する力を育てます。
- 行政や地域団体と連携した、涸沼を始めとする湖沼や森林での体験学習の実施
-
3R(リデュース・リユース・リサイクル)をキーワードに資源循環型社会をめざします。
- 3Rを学ぶため工場見学会の開催
-
海洋プラスチックごみ問題を考える機会を提供します。
- 先進団体との連携や情報収集による家族で参加できる場の提供
-
家族の健康と環境を守るため、より地域に密着した石けん利用普及活動に取り組み、日常生活の中に石けんを取り入れ実践する意欲を広めます。
- 『レッツ・トライ「石けん」ライフ~2023改訂版~』を活用した石けん学習会の開催
- 『レッツ・トライ「石けん」ライフ~洗濯編~』の作成に向けた情報整理及び冊子編集
- 省エネや再生可能エネルギーについて学び、理解を深めます。
平和国際交流
安心して暮らせる共生社会をめざし、平和・国際交流活動に取り組みます。
他団体などと協力・連携し、平和・国際支援、海外文化を学び、理解する活動に取り組みます。また、センター委員会などと、学習会を通して平和の学びや情報を共有し平和の輪を広げます。
- 子どもから大人まで、すべての世代と平和の大切さを共有し、継承活動に取り組みます。
- NPO法人日本ファイパーリサイクル連帯協議会や茨城県ユニセフ協会の活動を支援、協力し、貧困・紛争・災害に苦しむ世界各地の人々の未来を守るための取り組みを進めます。
- パルシステムの商品を通じて、フェアトレードや海外産地・現地の暮らしの現状や文化等についても学びます。
- 地域で暮らす外国人と交流することを通して、多文化共生を目指す取り組みをします。
食育
手づくりを基本とした食の大切さを伝え、実際に作る楽しさを体験して、感謝の気持ちを育み、食べ物を選ぶ力を身につけるための食育活動をおこないます。
- お米+一汁二菜(4つのお皿)のバランスの良い日本型食生活の大切さを伝えるために、コミュニケーションを大事にした楽しい食育活動を広めます。
- 地域で育まれてきた食材と料理を学び、広めます。
- 毎月1回定例会を開催し、出前授業の練習、意見交換、学習会等をおこない、幅広い年代に向けた食育活動を検討します。
- オンライン開催も視野に入れた、子どもや親子向けなどテーマ別の料理教室・食育出前授業をおこないます。
- 組合員向け企画や地域貢献できる活動として、幼稚園や保育園、小学校向けに「紙芝居」「パネルシアター」などの教材を使って、新たな形で食育の出前授業を検討します。
産直
食と農をつなぎ 心豊かな暮らしをめざし 産直活動をすすめます。
産直産地の取り組みを自ら学びパルシステムの産直を広く伝えます。
- パルシステムの「コア・フード」「エコ・チャレンジ」の生産者と交流して、産地の努力や農業の実態への理解を深めます。
- 産直産地の取り組みや現状を理解するために産地研修を実施します。
- さまざまな学習会を企画(オンライン含む)・運営し、産地のこだわりを広く伝えます。